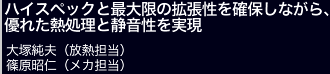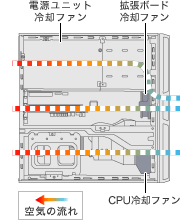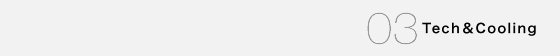
|
||||||||||
|
ツインユニットというコンセプトで、レイアウトフリーという極めて自由度の高い設置スタイルを実現したVAIO type R master。しかし、筐体を2つに分離したことで生まれるメリットと引き換えに、開発チームは数々の難問と直面することになった。たとえば、内蔵している多くの機器から出る熱や音の対策がそれだ。また、オーナーが触れる部分は前面と背面だけしかないのに、そこは吸気と排気の口として使用せざるを得ないという制約もある。そして、コンパクトなケースの中で最大限に求められる拡張性……。これらの問題をどうクリアし、優れた放熱性能と静音性をいかに実現したのか? 放熱担当の大塚純夫とメカ担当の篠原昭仁に語ってもらった。 篠原:type R masterは、本体を2つのユニットに分離したわけですが、これによって各ユニットの中に収められた部品の数が半分に減ったかというと、そんなことはありません。むしろ、逆に増えているのです。それでも、可能な限りコンパクトにするのが目標でしたから、どの部品をどこにレイアウトするか、ずいぶん考えました。しかも、本体の前面と背面は、排熱のために空気を通さねばなりません。このように、内部の機器のレイアウト、発熱と空気の流れ、騒音、という3つの問題をまとめてクリアするのに苦労しましたが、結果的にはかなり満足度の高いレベルに仕上げることができたと思います。 まず、拡張性についてですが、Full HDの動画を扱うとデータ量が格段に増えますから、ハードディスクも前面に4つ搭載できるようにしています。ちなみに、ハードディスクは簡単に取り外しができるよう、着脱式になっています。前面パネルとフロントパネルを外すと、ハードディスクのケースが見えますが、ケースについているレバーを引き、ケーブルを抜くだけで容易に取り外しが可能です。従来のRシリーズもハードディスクの交換は楽という評判でしたが、type R masterではこのようなメンテナンス性を、さらに高めています。 また、カタログには書いていないのですが、実はメインユニットの背面側にも、3.5インチ・ベイが2つ分用意されています。ハードディスクが4つでも足りないという方は、ここにハードディスクを増設することで、最大で6つのハードディスクを搭載することが可能です。(※) ※ご自身で増設された場合は、サポート対象外となります。 |
|
|
|||||||||||||||||
|
| 大塚:このように、type R masterは最大で6つのハードディスクを搭載できるほどの拡張性を備えているわけですが、実はその分だけ、騒音の発生源が増えるということなのです。以前は、騒音を抑えるために冷却用のファンを工夫するのが一般的でした。ところがファンの静音化が進むと、今度はハードディスクからの騒音の方が大きくなってくるという問題が出てきます。しかも、type R masterのハードディスクの位置は前面に4つある。つまり、従来のモデルに比べてオーナーに近い場所に、騒音源があるわけです。このような条件の中で、騒音をどう抑えるかが大きな課題でした。 ハードディスク関連の音には2種類あります。1つはハードディスクの内部から出る高周波の音。もう1つは、ハードディスクの振動から生まれる低周波の音です。高周波である内部の音に対しては、ハードディスクをアルミで覆うことで対処をしています。一方、低周波の振動については、ゴムのダンパーで抑えるという方法を採用しました。 篠原:ひと言加えると、ハードディスクを固定しているアルミの板の厚さも、いろいろと試行錯誤を繰り返し、最も振動の少ない厚さにしています。 大塚:それだけではありません。実はメインユニットの前面パネル、この裏には小さな穴が空いているのですが、これも防音効果があるのです。この穴はちょうど雪で作る“カマクラ”のように奥の方がひろがっています。この穴のことを「ヘルムホルツ共鳴器」というのですが、その効果で高周波の音を抑え込んでいるのです。ですから、前面パネルをつけておくと、さらに耳で聞き分けられるほどに静かになるのです。 篠原:発熱と騒音は、根本的に相反するものです。音を抑えるには、単純に密閉すれば簡単なのですが、そうすると熱がこもってしまいます。一方、熱を放出するなら穴を空けて空気の流れを開放すればよいわけですが、そうすると今度は騒音が漏れてしまう。だから、そのバランスをとるのが大変なんです。 大塚:使用中に突然「ウィーン」とか「ブーン」とかいう騒音が出るようなPCでは、高級感がありません。実際に、HD動画や静止画の編集・加工をしている際に、音が気になったら集中もできないでしょう。従来、type Rシリーズは静音性に関して「静かだ」という評価を得ていました。しかし、これだけのスペックを搭載した機種となると、さらに進んだ対策をとらないと騒音が漏れてしまいます。そのため、随所に防音対策を施して、これまでのtype Rシリーズ以上の静かさを実現したのです。逆説的にいえば、こうした騒音対策の徹底ぶりが、type R masterの高機能と高い拡張性を物語っているといえるでしょう。 |