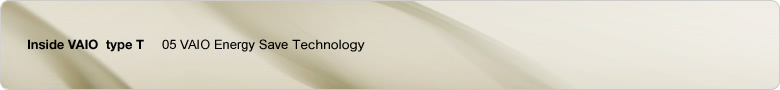従来はカタログ値におけるバッテリーの持続時間が重視されていたが、新type Tではより一般的な使い方での持続時間が重視されている。従来用いられていた省電力機能のほか、照度センサーなどを用いて自動的に省電力を行う機能が新たに取り入れられ、実使用時間は大幅に延長している。
現在、地球温暖化の懸念から省電力やグリーンITが注目されており、新type Tでも省電力に積極的に取り組んでいる。モバイルPCにおいては、省電力はすなわちバッテリー持続時間の延長につながり、ユーザーの利便性も高まる。
カタログなどに掲載されるバッテリーの持続時間は、JEITAの規格に従ったテスト結果だが、必ずしも実際の使用状況にあった状況でのテストではないために、実使用時間とのずれがあった。新type Tでは、実際の使用時間を伸ばすことを重視し、そのために数多くの機能を搭載した。
特に効能が大きいのは、照度センサーを用いたディスプレイ輝度の自動調整である。照度センサーは、周囲の明るさを計測するものだ。周囲の状況にあわせて、暗すぎず明るすぎない最適な輝度に調整する。これまでもホットキーを押すことで調整できたが、照度センサーを使うことでユーザーの手を煩わせることなく、最適な輝度に合わせられるようになった。
![]() モバイルPCはオフィスの机、会議室、電車の中、飛行機の中、取引先などいろいろな場所で使用します。同じ部屋でも、途中からプロジェクターを使うために照明を落とすこともあるでしょう。そのような環境で、その場にあわせてホットキーで調整するのはちょっと煩わしいため、最大輝度のまま使い続けている光景をよく目にします。
モバイルPCはオフィスの机、会議室、電車の中、飛行機の中、取引先などいろいろな場所で使用します。同じ部屋でも、途中からプロジェクターを使うために照明を落とすこともあるでしょう。そのような環境で、その場にあわせてホットキーで調整するのはちょっと煩わしいため、最大輝度のまま使い続けている光景をよく目にします。
しかし、液晶は電力消費量の大きいデバイスで、輝度を少し下げるだけでシステム全体の消費電力を大幅に下げることがすることもできます。オフィスや家庭などの一般的なPCの使用環境下では最大輝度を必要とすることはほとんどなく、最適な輝度に調整するだけで大幅にバッテリー持続時間を延長できます。そこで、自動的に輝度を調整させるために照度センサーを組みこみました。使用するソフトウェアによっては「もっと輝度がほしいな」というときもあるでしょう。そんなときは従来どおりホットキーで簡単に調整することもできます。
また、最適な輝度で使用することは目にもやさしく、仕事などで長時間使う場合は目の疲労も低減されます。最適な輝度がどのくらいかなかなかかわかりにくいですが、輝度の自動調整機能はそれを自動的に行ってくれます。
急速充電を使用すれば、50%までなら通常の約半分の時間で充電可能だ。急いでいるときに短い時間で充電を完了させることができる。しかし急速充電は使いすぎるとバッテリーのセルを痛めてしまう可能性もある。そのために新type Tにはセルを痛めないように配慮しながら充電するいたわり充電の機能も備えている。状況にあわせて組み合わせて使うことでセルの劣化を防ぎながらの充電が可能だ。
![]() 従来のtype T(VGN-TZシリーズ)と比べてカタログなどに掲載されるバッテリー持続時間はあまり変わっていないようにみえますが、実使用環境でのバッテリー持続時間は、省電力機能が大幅に強化されたことと、消費電力を抑えきれなかった部分を徹底的に対策することで、従来モデルと比べて約1.5倍長持ちするでしょう。実使用環境の定義は難しいですが、ここでは一般的なオフィスの明るさの場所にPCを置いて出荷時状態の設定のまま放置したときの時間で比較しています。メモをとったりWebを閲覧しているときって、PCはほとんど休んでいる状態なんですよ。急速充電にも対応したので、すぐに外出しなくてはいけないようなときでも最低限の充電を済ませられますから、ACアダプターを持ち歩く必要性も下がったといえます。
従来のtype T(VGN-TZシリーズ)と比べてカタログなどに掲載されるバッテリー持続時間はあまり変わっていないようにみえますが、実使用環境でのバッテリー持続時間は、省電力機能が大幅に強化されたことと、消費電力を抑えきれなかった部分を徹底的に対策することで、従来モデルと比べて約1.5倍長持ちするでしょう。実使用環境の定義は難しいですが、ここでは一般的なオフィスの明るさの場所にPCを置いて出荷時状態の設定のまま放置したときの時間で比較しています。メモをとったりWebを閲覧しているときって、PCはほとんど休んでいる状態なんですよ。急速充電にも対応したので、すぐに外出しなくてはいけないようなときでも最低限の充電を済ませられますから、ACアダプターを持ち歩く必要性も下がったといえます。
数多くの省電力機能を搭載した新type Tでは、設定が複雑になることが想定された。それを避けるために、省電力機能をひとつのユーティリティーに集約した。このユーティリティーだけで、新type Tが持つすべての省電力機能を管理し、その効果がどれだけあるのかを知ることができる。
![]() 省電力の機能は使わなければ搭載しても意味がありません。ところが従来の省電力機能は多岐にわたるうえ、設定画面も分かれていて、どこで調整すればいいのかがわかりにくいという反省がありました。そこでひとつのユーティリティーに集約し、S1ボタンから起動できるようにしました。さらに、「VAIO 省電力ビューア」ではユーザーの方にもバックライトの消費電力がリアルタイムで見えるようにしました。省電力の「見える化」ですね。
省電力の機能は使わなければ搭載しても意味がありません。ところが従来の省電力機能は多岐にわたるうえ、設定画面も分かれていて、どこで調整すればいいのかがわかりにくいという反省がありました。そこでひとつのユーティリティーに集約し、S1ボタンから起動できるようにしました。さらに、「VAIO 省電力ビューア」ではユーザーの方にもバックライトの消費電力がリアルタイムで見えるようにしました。省電力の「見える化」ですね。
新type Tは、従来の路線を継承しつつ、新しい時代の先駆けとして多くの機能を取り入れている。それは256GBのSSD、SSDとブルーレイディスクドライブの両立、ノイズキャンセリングなど世界初、世界最小となる機能を満載していることからも明らかだ。しかしむやみに世界初を目指したわけではなく、ユーザーの利便性を高めようとしていたら世界初がたくさん出てきたというのが実のところである。「もっとも人に近いところにあるPC」それが新type Tの示すモバイルPCのあり方だ。