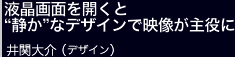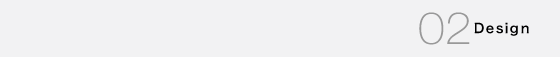
|
|||||
|
�V����type A�́A�m�[�gPC�Ƃ��Ă͔��ɑ傫�ȃ{�f�B�������Ă���B�������A������ƁA�����ɂ͗]���ȃX�y�[�X���܂������Ȃ��قǁA���܂��܂ȃp�[�c���r�b�V���Ƌl�܂��Ă���BFull HD���������邽�߂ɂ́A���ɑ����̃n�[�h���K�v�������̂ł���B�����̕��i�ʂȂ����߂Ȃ���APremium�ASilent�AThin and Slim�Ƃ���3�̃L�[���[�h�ɉ������f�U�C���Ɏd�グ�邱�ƁB���ꂪ�A�f�U�C�i�[�̈�֑��ɗ^����ꂽ�~�b�V�����������Btype F�Ȃǂ��肪���AVAIO�m�[�g�̃X�����f�U�C����Nj����Ă�����ւ́A����̃f�U�C�����[�N�ɂ��Ă������B ��ցFPremium�Ƃ������Ƃł́Atype A�͂�����t���b�O�V�b�v���f���Ȃ̂ŁA�n�C�X�y�b�N�ȃm�[�gPC�ł���Ƃ������Ƃ������ڂ�����`����Ă���A�������̂���f�U�C����Nj����܂����B���̑�\���g�v���~�A���u���b�N�h�Ƃ����A�t���p�l���̔w�ʂ̌���d�グ�ł��B���͂��̕����AVAIO�ł͂�����݂̃}�O�l�V�E��������f�ނƂ��Ďg���Ă���̂ł����A����d�グ�Ƃ����̂͒ʏ�̓h������Ԃ������邤���A���Ƀ}�O�l�V�E���̒������i�ɑ��Č���h���d�グ���s���̂́A���ɓ�Փx�������̂ł��B �}�O�l�V�E���̒������i�ɓh������ꍇ�A��ʓI�Ȏ菇�Ƃ��ẮA���^��ɍr�����A�h�K�����A���n�i�v���C�}�[�j�h���A�Ō�ɒʏ�̓h�����s���܂��B����ɑ��A����͊e�H���ɔ{�ȏ�̎�Ԃ������邱�ƂŁA��荂�i�ʂȌ���d�グ���������܂����B��̓I�ɂ́A�r�����H���Ń��{�b�g���g�p���A�Ȃ������X���̖ڂ̑e�������x���������s������A���n�̃v���C�}�[��2��ގg�p����ȂǁA�h��������O�̑f�n�̏�Ԃ��A��蕽���ɂȂ�悤�H�v�����܂����B�������Ďd�オ�����\�ʂɁA�u���b�N�h���A�N���A�[�������{���A����ɓh����A�ЂƂЂƂ��ƂŖ��������Ďd�グ�Ă��܂��B���̂悤�ɁAtype A�̔���������d�グ�́A�v�`�[���̋��͂ɂ��������Ă��܂��B |
| ����ɑ��āA�t���f�B�X�v���C���J������Ԃł́ASilent�Ƃ����L�[���[�h���l�������f�U�C�����{���A�g���Ă����Ԃł͑��`�Ƃ��Ẵm�C�Y���Ȃ��A�g�Â��ȁh�f�U�C���ɂ��܂����B�V����type A�́A���i�ʂŔ�����HD�R���e���c�������}�V���B����Ή�ʂ�����ł��B�����ŁA��ʂ̒��ɉf��f��������ɂȂ�悤�A�R���e���c���y����ҏW����Ƃ��ɁA�܂�肪�ז��ɂȂ�Ȃ��悤�ȃt���b�g�ȃf�U�C���œ���B���Ƃ��A�t���[�e�B���O�f�U�C�����̗p���邱�ƂŁA�t���f�B�X�v���C���x����q���W�������Ȃ��A�f�B�X�v���C�����ɕ����Č�����悤�ɂ�����A�x�[��������ʂƓ�������Ƃ��邱�ƂŁA��ʂ̎��͂̈�ۂ��������A�N���A�u���b�N�t�������ۗ��悤�ɔz�����܂����B |
|
�@ |
|
||||||||||||||||
| �L�[�{�[�h���ӂ��A��ʏ�ł̍�Ƃ��ז����Ȃ��悤�ɁA�ł��邾���t���b�g�Œi���̂Ȃ��X�b�L�������f�U�C���ɂ��A���̒��Ŏg���₷����Nj����܂����B���Ƃ��A�L�[�̎��ӂƃp�[�����X�g�̕����ɂ�1.3mm�̒i����݂��Ă��܂��B���� Curve�p�[�����X�g�ɂ���āA��ƒ��̎���x�߂邱�Ƃ��邱�Ƃ��ł���̂Ɠ����ɁA�f�U�C����̃����n���ɂ��Ȃ��Ă��܂��B�܂��A�p�[�����X�g�͓���I�ɐG�镔���Ȃ̂ŁA������LCD���ƈႢ�}�b�g�ȃu���b�N�ɂ��܂����B �܂��Atype A�ł͔������d�v�ȃe�[�}�ł����B�@�\�����ڂȂ̂Ń{�f�B���Ԍ����Ȃ�܂����ł́AVAIO�Ƃ��ċ�����܂���BThin and Slim�Ƃ����L�[���[�h�ŁA�����ɃX�����ɂł��邩�𐏏��ŒNj����܂����B���Ƃ��A�{�̂̃T�C�h�̎d�グ�ł́A3D�̃��f�����O�ʼn��p�^�[�����`����������A�������������Ƃ����f�U�C���ɂ��܂����B����ɂ���āA�{�̂̉����������ĕ����Ă���悤�ȃf�U�C���ƂȂ�A�`��̗͂Â悳������A����������悤�ɂȂ��Ă��܂��B �����ɖ{�̂𔖂��ł��邩��Nj����ׂ��A�R�l�N�^�̔z�u���͂��߁AHDD��e���r�`���[�i�[�Ƃ������f�o�C�X�̃��C�A�E�g���A�v�̕��Ɖ��x���������s���Ȃ���f�U�C����i�߂܂����B�܂��A�{�̃T�C�h�ɏ������b�L�ɂ��V���o�[�̊��炩�ȃ��C���������Ă��Ă��܂��iAR50B�̓V���o�[�h���j�B���̕����́A3D�̃��f�����O�ʼn��x���`����������A�{�̂��瑤�ʂɂ����Ĕ��ˌ��ɂ��͋�����ۂ�^���A�{�̂̉������������݁A���{�̂̔������������邱�Ƃ�_���܂����B�ȏ�̂悤�ɁA�ގ��̎��������┽�˂𗘗p���Ȃ���APremium�ASilent�AThin and Slim�����������̂�type A�̃f�U�C���Ȃ̂ł��B |