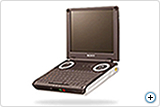映像、音楽、写真、コミュニケーションなど、私たちの身の回りのものごとはどんどんデジタル化され、便利に楽しく進化してきた。その中で光る存在であり続けてきたVAIOも誕生してから10年余。改めて現場の開発者それぞれが持つVAIO観を聞いた。
━━ まず、ものづくりの源流にいるおふたりのVAIO観とは何でしょうか。
伊藤
VAIOは、その時代時代のモバイルPCのあり方を考えて、提案してきた製品だと思っています。これはVAIOに限らず、ソニーの製品に共通して当てはまることかもしれません。
振り返ってみると1997年から発売されたモバイルPCでいうとバイオノート505、バイオC1、バイオGT、バイオU、type Uなど、その時代とその先にあるものを捉えて、新しいPCのあり方を提案してきました。そこから、驚きや感動、所有する喜びを生み出せるものがVAIOだと思ってつくっています。

━━ 具体的にいうと、いまはどういう時代なのでしょうか?
伊藤
いまコンピューティングの世界がPC以外のさまざまな機器にも広がっています。ケータイやスマートフォンがネットワークにつながって、メールやネットサーフィンならばどこでも楽しめます。こうしたことは10年前とは全然違います。そして誰もがケータイを持ち歩き、写真を撮ったり、ブログを更新したりしているのが今の時代です。そこで今回、ケータイとともにいつでも持ち出したくなるモバイルPCとはどうあるべきかを、ゼロから考えました。

詫摩 見方を変えると、私たちにとってPCは生活に欠かせない時代になりました。だからPCがワクワク、ドキドキするものだと生活がもっと楽しくなるはず。VAIOはそういう存在であり続けたし、これからもそう。type Pに限らずVAIOをデザインする際はパッと見たとき、触って使ったときに、どんなワクワク、ドキドキを提案できるかをいつも探しているんです。
━━
デザイナーという立場で何が提案できるか探すとは、具体的にいうとどんなことをしているのでしょうか?

詫摩 自分はPCが大好きなんです。製品を使っているのも好きだし、試作品をいくつも試させてもらっているだけで楽しい。表層的な美しさもさることながら、使いざまからくる形のありかたを考えると夢中になってしまう。今回のtype Pのようなプロジェクトが始まると本当にうれしくて、街に出てカフェに行っても、旅行先でのんびりしていても、自分だったら何に使おうか、こんな形だったらこんなことができるのにと想像したりアイデアを膨らませたりしてます。こうなると仕事もなにも関係なくなる(笑)。朝会社に来て帰るまでが仕事ではなく、全ての生活シーンでPCのことばかり考えています。
━━
伊藤さんのお話にもあったようにVAIOは、バイオC1、type Uなど、モバイルPCの分野でも先駆的な存在であり続けたと思います。
このような背景を持つ、今回のtype Pはどのような存在なのでしょうか?
鈴木
私の中には“小さいもの”に対する強い思い入れがあります。過去にtype Uを担当したことがあるのですが、小さいVAIOは私にとっては特別です。これはVAIOだけでなく、ソニー自体に小さいものを作ろうという遺伝子というか、魂があると思っているからでしょうか。なんか小さくしたくてしょうがない人が集まっているんです(笑)。いろいろな事情で小さくできないものを、何とか乗り越えたり、押さえ込んだり、デザインも含めて小さくまとめたいという性分なのかもしれません。

花塚 私たちはバイオノート505以来、小型化、薄型化、軽量化にチャレンジしてきました。確かにソニーにいる人は、みんな製品を小さくしたがっているところはありますね。
川上
今回のtype Pは、最初からハードルが高いところにありました。当初は、このサイズの中に部品が入りきる気がしなかったので・・・。それでもデザイナーの話を聞いたり、モックを見せてもらっていると、だんだん“これは欲しいな”という気持ちがふつふつと沸いてくる。そうすると「自分の担当部分でダメにしてはいけない」と思うようになるんです。そういう中でいかに妥協をしないで、デザインをキープした状態で、電気回路を中に収めるか。しかも使い勝手やスペックも損なわずにというハードルがありました。

━━ 壁にぶつかったとき二者択一ではなく、最大公約数を見つけていく。その気構えがすごいですね。皆さんは、なぜ諦めずに小さいものへチャレンジできのでしょうか?
花塚 苦労があるのは事実ですが、使う人のことを考えると、やり遂げなくてはと思う。より多くの人に使ってもらえると私たちもうれしいですし。
鈴木
一番小さいVAIOだけが突飛なことをやっているところが、これまでもありましたね。逆にそれがVAIOのトンがったところでもあるのですが。モバイルPCの分野が賑やかになっている昨今、ソニーの小型化技術を発揮できる得意分野で勝負できるという意味で、やりやすい面もあります。

少し前まではtype Uくらいしか選択肢がなかったのですが、現在は市場環境が一変しています。今回のtype Pは、僕らがいま小さいものを作ったらこうなりますというひとつの解です。他社さんから似たようなスペックのモバイルPCがたくさん出ていますが、お客様への選択肢として、ソニーの得意分野であるモバイル性能(薄、軽、スタミナ)で差異化ができる商品を投入できるというのは、ある意味で幸運だと思っています。あと、モバイル機器全般で見ると、ケータイやスマートフォンのインターネットコネクティビティーが高まっていて、以前のようにPCだけがインターネットにつながる機器ではなくなりつつあります。これまでケータイなどでのインターネットしか体験したことがない若者にも、フルスペックなインターネットの世界を伝えたい。type Pには、そんな想いを込めています。
━━ PCは技術革新が次々と起こるうえ、水平分業が進んでいるため参入障壁が低い。そういう意味で競争が激しい分野です。その中でVAIOは特別なポジションを築いてきていますが、どのようなことを心がけているのでしょうか?
伊藤 自分たちがどれだけ想いを込められるか。生命を宿すような作業をしていると思います。細部まで熱く議論をしながら、どうあれば良いかを決める過程でVAIOらしさが醸成されるのでしょう。
鈴木
設計者が想いを込めるときって“会ったことがないお客様が見たときにも、我々の想いが製品からにじみ出ることが絶対にあるはず”と信じるんです。デザイナーが作ったかっこいいモックに想いを込めていく。そこでは気合いが必要で、それがないとどこか間の抜けたものができてしまう。

川上 確かに見た目がかっこよくないと、モチベーションのスイッチが入らないですよね。
小野
僕も作った人の想いは必ず伝わると信じています。コンサバに作ればその程度しか伝わらないし、苦しいけど良いものを作りたいという気持ちを込めると、そこは伝わる気がしています。変な精神論かもしれないけれど、不可能を可能にしたり、理屈を超えて人の心が動くときって、そういう思いがあるような気がする。VAIOには、そういうスピリットが込められているんです。
個人的には、見せびらかせたくなるようなモノを作りたい、持っているだけで、カバンの中にあるだけでニヤッとしたくなるようなものを作りたかった。そうでないと、VAIOとして、このロゴをつけて、買ってもらって、喜んでもらう領域にはたどり着けないのではないかと思っていましたので。