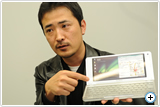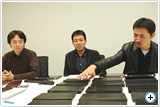ワイヤレスアクセス網の整備と料金の低廉化、これにともなうモバイルPCの進化や機器の多様化で、いつでも、どこでもインターネットと繋がっていられる環境はますます充実してきている。こうした時代背景の中で、VAIOに何が求められているか、VAIOは何を提案できるのか。開発者たちは考えた。
━━ インターネットがより身近になっていく時代の中で、VAIOには何が求められていますか?
詫摩
仕事、プライベートを問わず、パッと思いついたことを残しておきたいと思ったとき、僕はキーボードで文字を打ちたいんです。もちろんケータイでチクチク打って送るっていう手もあるのですが、そうしているうちにアイデアが飛んで行ってしまう気がする。カフェでお茶を飲みながら、あっ、って思いついたアイデアを残したい欲求は強いし、それにはPCのキーボードが一番早い。仕事以外の文章でも、言葉でも、詩でも、なんでもかんでも。これだけPCが身近になってきているので、僕が感じているそういうところに共鳴してくれるユーザーって少なくないと思うんです。

川上 私自身はいつか手帳のように使えるモバイルPCが作りたいと思っています。どっこいしょ、さぁなんかやるぞって構えた感じでやるのではなく、カジュアルに持ち歩いて、メモしたり、メールをちょっと書いたり、手軽に写真を撮ったりできる。そんなモバイルPCを求めていました。
詫摩 キーボードを打つことは、今では当たり前の作法のようなもの。ペンで文字を書くのと同じくらいキーボードで文字を打ち込むことが一般的になってきています。ただそのときに僕たちが使いたいのは書き心地が良く、持っていてもうれしい万年筆。だから(両手をキーボードに乗せる構えをして)こういうスタイルで快適にキーボード入力できることは大事にしました。
━━ 今回のtype Pは、外に持ち出して使うことを第一に考えて作られている。具体的なシーンはどんなイメージですか?
伊藤 私は週末は新しいスポット巡りに行きたい派なんです。たとえば出かけた街で、この近くに新しいスポットがないかな、イベントがないかなと思う。いまだったらインターネットにアクセスし、地図のサイトで周辺のスポット情報を探せますよね。そんなことを外出先でも手軽にできるVAIOがあればインターネットはもっと楽しくなるし、生活がもっと便利で豊かになると思う。その解がtype Pだと思っています。
鈴木
たとえば検索エンジンで何かを調べると、検索結果がたくさん出てくる。その中から自分が知りたい情報をパッと選びたい。そのためには大画面で高解像度なディスプレイも必要だと思うんです。そんなことを考えて、type Pは横長かつ大画面。1600×768ピクセルという液晶を採用したのは、type Pならではの使い方を考えた結果です。

伊藤 地図サイトを表示しても、きちんと地図が見える縮尺で2画面並べられる。これがタテ、ヨコどちらが少なくても使い勝手は損なわれてしまう。外出先でインターネット上の地図を見ることは、強く意識した利用シーンです。
小野 ソフトウェア開発の立場で言うと、PCのスペックが進化し、OSも機能強化されているので、もっと生活が便利になってもいいと思う。では、何が必要か? と考えた例を挙げると、夢は壮大ですが、その一歩というところで、GPSなどで位置を捕捉、それも建物の中でも測位し、自分のいる場所がわかる。本当はうれしい。大きなターミナル駅や商業施設の中で、自分がどこにいるかわからなくなることがありますよね。そこで使えるものが何か提案したかったんです。このようにいつでもどこでもtype Pがそばにあることを前提としたら、ただテキストを打ちたいわけでもないだろうし、メールを打ちたいのではないと思う。何ができるかなというところを考えて、アプリケーションを作ったり、使い方を考えてできたのがtype Pです。
━━ PCとは本来はパーソナルなコンピューターのことですよね。でも実際には、このような感覚で使っている人は多くないとも思います。持ち主がもっと楽しくなったり、自分が表現できたらいいなと思うのですがtype Pにはどんな提案があるのでしょうか?
伊藤
type Pの企画当初、これを“ウェブパレット”と呼んでいたことがあるんです。形が絵の具のパレットに似ていることがモチーフなのですが、パレットって絵の具を乗せて、(その絵の具で)キャンバスに絵を描きますよね。type Pという“パレット”をつかって、Webという“キャンバス”に向かって自己表現をしてもらいたい、いつでも、どこでも持ち歩いて何かを発信して欲しいそんな願いがあります。
電源オフの状態からすぐに起動して、インターネットにつながる「インスタントモード」をつくったのも、5分程度のちょっとした合間でも使ってもらいたいという想いからです。これもVAIOが新しくチャレンジしている領域だと思います。

小野
Webを見るだけならほかの選択肢があったかもしれないのですが、我々が作りたかったのは万年筆。そうした観点で選んだOSがWindows Vistaなんです。私がソフトウェア担当ながら驚いたのは、type PでWMV 1080pのフルHD映像がきちんと再生できること。<ブラビア>の大画面に出力しても、全画面できっちり見られる。これはWindows Vistaとインテル Atom プロセッサー(Z500シリーズ)の組み合わせならではの価値で、普通のPCに迫る性能を実現していると思っています。
ただ、それだけで満足していいのかという問題意識もありました。持ち運ぶ機器のモチベーションのひとつは、外出先などでパッと使えることだと思います。そうしたニーズへの解が「インスタントモード」でした。無線LANスポットなどで、パッと取り出して、サッとインターネットにアクセスできる。重量級だけどリッチに動く、万能ではないけれどフットワーク軽く動けるという両方の選択肢を設けたことで、ユーザーのアクティブな生活を支援できるのではないかと思っています。