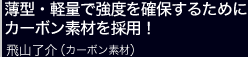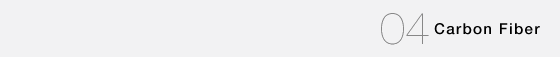
|
|||||
|
より薄く、より軽いモバイルマシンを実現する。そのために、同時進行で達成しなければならない技術的なポイントがある。それは強度の確保だ。薄くて軽いものほど、剛性を持たせて丈夫に仕上げる必要がある。そのために、新type Tではカーボン素材が採用された。カーボンといえば、VAIOノート505エクストリームから採用され、初代type Tでも限定モデルで採用された。カーボン素材担当の飛山了介は、その理由についてこう語る。 飛山:今回の新type Tでは、液晶ディスプレイが非常に薄型になりました。なるべく薄くするにはどうしたらいいかを考えると、やはり強度が必要になります。この薄さで強度をもたせようとしたら、カーボンでないと支えきれないだろうと思いました。マグネシウム合金で考えると、内部構造の実現のためにダイキャストの製法を選択することになります。これは金属を固めるものなので、結合としては硬いものになりますが、薄くしてゆくと結構脆くて、割れてしまうことがあり、今回のような形状には不利になります。その点、カーボンは繊維なので割れにくく、結果強度を保って薄型化できるわけです。 液晶ディスプレイに採用したマルチレイヤーカーボンファイバーは、まさに数枚のカーボンのシートを重ねて作った板です。厚さはわずか0.7mmしかありません。ちなみに、従来のマグネシウム合金設計と比較して、マルチレイヤーカーボンファイバーは比剛性で約2倍。しかも30%の軽量化を達成できました。 ディスプレイが軽量化すると、それを支えているヒンジにかかるトルクを下げることができるので、ディスプレイを開閉する際に必要な力が少なくてすむというメリットがあります。新type Tの液晶ディスプレイはスムーズに開閉できるようになっていますが、これは軽量化によって使い勝手の向上につなげることができた例なのです。 |
|
同じカーボンの採用でも、VAIOノート505エクストリームのときと今回の新type Tでは、実はずいぶん事情が違ったという。新type Tは多くの台数を量産するモデル。そのためには、量産性を向上させる必要がある。数が作れなければ致命傷になるからだ。 飛山:量産化のために歩留まりをあげる事を追求し、マルチレイヤーカーボンファイバーの基材、製造設備、製造方法など新type T生産に関する全てのものを『量産化実現』の観点で、ソニーと今回の新type Tに関わったメーカーさんで知恵を絞りました。 企業秘密に関わるほどのノウハウなので詳しい説明はできないのですが、初代カーボンモデル『505エクストリーム』、2代目『type Tカーボンエディション』で得た様々な知見をベースとし進化させた最新の技術・ノウハウを今回の新type Tには多く投入しています。 そしてこの最新技術・ノウハウを何度もトライ&エラーを繰り返して練り上げていきました。トライ期間中は、「気が付けば朝」という事が何度もありました。 このように様々な技術・ノウハウを集め、徹底的にブラッシュアップした事で『マルチレイヤーカーボンファイバー』の量産化が実現できたのです。 |
|
新type Tでは、液晶ディスプレイの天板部分にマルチレイヤーカーボンファイバーを採用し、本体の底面にはカーボンモールドを採用している。同じカーボンでも場所によって使い分けをしているのである。カーボンモールドは、プラスチックの樹脂に微細なカーボンの繊維を練りこんだ素材だ。こうした適材適所の使い分けについても解説をしてもらった。 飛山:カーボンモールドを作る場合、プラスチックの樹脂にカーボンの繊維を混入する率を増やせば、強度は実現できます。ただし、プラスチックは流しこんで成形をする素材ですが、カーボンは溶けないので流れにくいのです。単純に混入率を増やせばいいわけではなく、強度と加工のしやすさのバランスから、ちょうどいい材料を厳選し、その結果、重さは同じで強度は通常の樹脂の約4倍という高い剛性を確保しました。 なぜ、天板にはマルチレイヤーカーボンファイバー、底面にはカーボンモールドと使い分けたのかというと、ディスプレイの側はフラットな板状で、中に構造物がほとんど存在しないためです。こういう場合は板状でも剛性の高いマルチレイヤーカーボンが最適です。 一方、本体の底面はメモリーを収めるための蓋があったり、内部の構造物があるために、形状が複雑です。底面に使う場合は、一発で形状ができあがってきて、ある程度の構造も作れるカーボンモールドが適しているというわけです。カーボン素材を使い分けたのは、こうした理由からなのです。 |