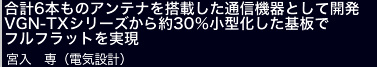|
|||||
|
新 type Tは、その薄くコンパクトなボディに6本ものアンテナを内蔵している。まず無線LANのアンテナが、送信と受信あわせて合計3本。 これは、複数のアンテナによって100Mbpsオーバーの高速通信を可能にするMIMO(Multiple Input Multiple Output)に対応したためだ。そして、Bluetooth、FeliCa。さらにはワンセグも搭載している。まさに通信機能満載の1台である。電気設計を担当したエンジニアの宮入専はこう語る。 宮入:6本ものアンテナを搭載する時代を迎え、作り手の側からすると、モバイル系のVAIOノートはもはや通信機の領域に入ったと言えます。そこで、今回の新 type Tの開発では、新たに評価用の設備を導入し、通信機器としてのより厳しい条件で開発を行いました。また、ノイズを下げるための設計ツールを独自に開発しました。このような充実した開発環境を整え、設計作業に取り組んだのです。 |
|
こうした取り組みによって、新 type Tの通信機能はさらなる進化を遂げた。それが最もわかりやすい形となっているのが、いまやモバイルPCには欠かせない存在となったワンセグだ。驚くなかれ、新 type Tのワンセグは、アンテナが液晶ディスプレイのベゼルに納められており、右上から伸びるようになっているのである。 宮入:ワンセグのアンテナは、これまで本体の側面(液晶ディスプレイの根元の横側)にありました。しかし、この場所だとシステムから発生するノイズの影響を受けやすくなり、ワンセグの受信感度が落ちてしまうケースが出てきます。我々の間では「自家中毒」と呼んでいる現象です。もちろん、ノイズを抑える努力は以前からしていますが、今回はそれに加えてアンテナを液晶上部に配置することで受信性能を向上させました。当初は、ベゼルの中にワンセグのアンテナまで入れるスペースがなかったのですが、デザイナーの井関の「本体側面にはアンテナをつけたくない」という強いこだわりもあり、無線LANのアンテナをさらに小型化するなどの努力によって、ワンセグのアンテナ1本分の空間を作り出したのです。 |
|
|
|||||||||||||||||
|
PCの性能はこの10年間で飛躍的な進歩を遂げたが、それによってハードウェアも複雑になった。性能向上によってサイズが大きくなるのは宿命であり、そこに開発者のジレンマがある。新 type Tの開発チームは、究極のフルフラットボディを実現するために、今回そのジレンマに果敢に挑戦した。その結果実現されたのが、最新のデュアルコアCPUを搭載しながら、VAIO type Uとほぼ同サイズの約10cm×10cmという、超高密度の小型基板だ。ひとつ前の機種であるVGN-TXシリーズから約30%も小型化した基板を手にしながら、宮入はこう語る。 宮入:従来は、PCカードスロットと基板を重ねてレイアウトするなど、部品の配置を工夫することで、限られたスペースの中で高性能を実現していました。しかし、新 type Tの場合はこれまで以上に薄さを追求したフルフラットモデルなので、部品を重ねることができません。そこで、基板のサイズを小さくするために、部品の小型化を推し進めながら無駄な部品を徹底的に省きました。具体的には、パワーマネージメント用のマイコンを従来の約4分の1のサイズにしたり、CPUの周辺にズラリと並んでいたコンデンサーをわずか3個にまで減らしています。こうした緻密な作業を、部品ベンダーと共同で行いました。 また、アーキテクチャーの持つ本来のパフォーマンスを下げる事なくここまでの小型化ができたのは、電気設計から機構設計、熱設計や製造関係者までが、1ヵ所に集まっている開発環境が大きいですね。全員が1台のCADの前に集まって、実際の開発に入る前にシミュレーションを行いながらディスカッションすることで、「バーチャルな作り込み」が十分にできるのです。この新しい開発スタイルこそが、新 type T誕生の原動力になったと思います。 |