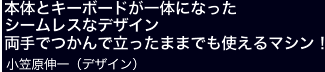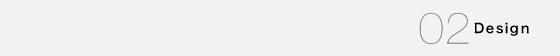
|
|||||
|
方向性が決まったマシンに具体的な形を与えたのが、デザイナーの小笠原伸一だ。実は、小笠原には以前から温めていたアイデアがあったと言う。Uシリーズの「U」は「ユビキタス」の「U」であるという持論のもと、初代のバイオUが発表された後に、独自でスタディーを行いモックアップまで試作していたのだ。当時の技術ではタブレット型が限界だったが、この間のデバイスの進化によりさらに小型のPCの開発が可能になった。まさに満を持していた状態で追い風が吹いたわけだ。type Uの開発に臨んで、数年間温めていたアイデアを投入した小笠原はこう語る。 小笠原:今回、type Uのデザインを担当するにあたって最初に考えたのは、初代のバイオUから数えて4代目と言うことで、デザインも“第4世代”にふさわしいものを目指そうということでした。完成したtype Uを手前から見てもらうとわかるように、実際にU字型のシルエットになっています。これは、初代のバイオUを出した後で将来の進化形を想定してタブレットPCのようなものもモックアップで作り、両手で持って使うPCをデザインする場合の、画面と操作部分の関係などをスタディーしたときに考案したアイデアです。そのときから、これを活かせる状況が来たら使ってみたいと思っていました。 具体的なデザイン作業では「本体とキーボードが一体でありながら、使いやすを実現するにはどういう形状がベストか?」を念頭に行いました。U字型のシルエットを採用することで、キーを打つときにホールドできるようになります。また、キーボードはもちろん、ポインティングデバイスやボタン類も、ホールドする部分の中にまとまって配置するようにすることで、ほとんど親指だけで操作が可能になり、立ったままでも快適に使える、“第4世代”のモバイルグリップ・スタイルが実現できたと思います。 |
| 今回のデザインで特に気をつけたのは、見たときのスッキリさと、触ったときのシックリさの両方を追求するということです。前者は、驚くほど多機能で盛りだくさんの内容なので、バッテリーの部分がどうしても厚くなるとか、アンテナ配置など物理的な制約が出てくるのをどうやって小型化し、スッキリとまとめるかということです。また、後者はホールドしたときに角の部分が手に当たって痛くならないようにするとか、グリップ部分の形状をいかに手に馴染むようにするかということです。 そのために、手で握ったときの感触をモックアップで確かめながら、グリップ部分の形状を詰めていくという検討を何度もしました。手に馴染むということでは、ポインティングデバイスの材質にもこだわりました。従来のゴム製だと指先がどうしても滑ってしまうので、精密金型加工という高度な技法を使って ゴムの表面をギザギザに加工しています。これによって、触ったときの指先がグリップしてカーソル操作が快適になっています。 |