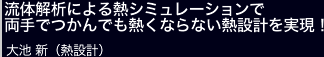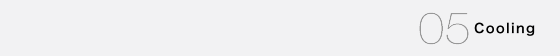
|
|||||
|
VAIO type Uのコンパクトなボディには、サブノートPCであるVAIO type Tと同等の回路が収められている。快適にWindows環境が使えるフル機能のPCを、小型化・省電力化などの技術とノウハウを用いることで、片手でつかめるバイブルサイズに落としこんだわけだ。当然、そこには発熱の問題が立ちはだかることになる。そこで登場してもらうのが、発熱設計を担当したエンジニアの大池新だ。PCの本体を、両手でつかんで使うというモバイルグリップ・スタイルならではの“ホット”な問題と、それにどう対処したかという“クール”な解答に耳を傾けて欲しい。 大池:発熱の問題は、PCの高性能化にともなって年々大きくなっています。特にtype Uの場合は、モバイルグリップ・スタイルということで、本体を手に持って操作するため、使用中に熱くなったりしては困ります。そのため、普通のノートPCよりもさらに徹底した発熱対策が必要でした。いろいろなことをやったのですが、開発の初期の段階から行った、排気のシミュレーションは非常に貢献していますね。 具体的には、熱流体解析と呼ばれる手法を使って、筐体のどこに穴をあけてどういう空気の流れにしたら、熱処理的に有利になるかをシミュレーションしました。そのシミュレーションの結果に基づいて、「これよりも部品を動かしたら絶対に熱が上がりますよ」という感じで、部品を収める際の線引きをしました。基準を作ってそれを守ることで設計を進めれば、大きな破綻は起こらないわけです。そのぶん電気やメカのメンバーは大変だったと思いますが(笑)。 |
|
|
||||||||||
| その他にも、細かい工夫をいろいろと行いました。たとえば冷却用のファン。今回のセットにあわせてファンを最適化しました。ブレード形状を新しくすることで、同じサイズの従来のファンに比べて風量が10%アップしています。また、筐体の内部にある構造材(ボディの補強材)を放熱板として利用することで、セット全体で冷やせるようにしています。放熱のために、構造材をここまで積極的に使ったのはtype Uがはじめてです。 さらに、見えない部分での工夫ですが、筐体の内部にフレーム構造を採用しています。これは、メインの基板と発熱するデバイスを組み込んだフレームが、宙に浮いているような構造です。このフレーム部と筐体との接続箇所を最小限にすることで、熱が伝わるのを最小のレベルに抑えているのです。これは元々、本体を落とした場合の耐衝撃性も兼ねた工夫です。内部でフレームが浮いている感じになっているので、外からの衝撃が伝わらないのと、発熱が外へ伝わらないのと、2重の意味での設計が施されているわけです。 |